 冬に起こる下痢の原因
冬に起こる下痢の原因 冬の定番・鍋料理でなぜ下痢に?
冬の寒い時期、体を芯から温めてくれる鍋料理は、食卓の主役です。野菜がたっぷりとれ、栄養バランスも良いため「健康的な食事」の代表格ですが、実は「鍋を食べると決まってお腹を下してしまう」という悩みを持つ方は少なくありません。 なぜ、体に良いはず...
 冬に起こる下痢の原因
冬に起こる下痢の原因  下痢の基礎知識
下痢の基礎知識 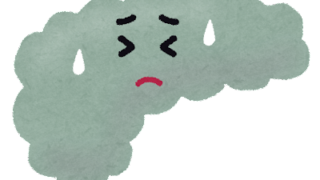 下痢の原因
下痢の原因  食べ物・飲み物による下痢
食べ物・飲み物による下痢  夏に起きる下痢の原因
夏に起きる下痢の原因 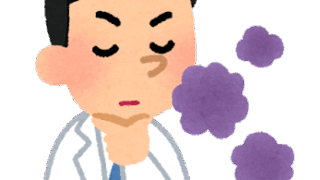 コラム
コラム  下痢と腸内環境
下痢と腸内環境  下痢の基礎知識
下痢の基礎知識  下痢の基礎知識
下痢の基礎知識  夏に起きる下痢の原因
夏に起きる下痢の原因